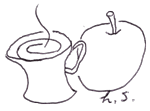映画『竜とそばかすの姫』

(C) 2021 スタジオ地図
要するに、仮想デジタル空間のなかで、アバターを脱ぎ捨てて、コミュニケーションをとりたい相手に接することも、必要だ、ということのようだ。
どちらかというと、クリエイティビティーが少なすぎる。唯一、それがあると感じられるのは、竜がじつは遠くで虐待を受けていた少年だった、という点だろうか。
はじめから4分の3くらいまでは、脈絡もなく、必然性もなく、伏線とおぼしき場面をちらばせて、つながっていく。セリフにも深みが欠ける。
宮崎駿やディズニーのアニメからや、「魔法少女まどか☆マギカ」かららしきキャラクターが、堂々と重要な脇役を演じている。これをオマージュとでも呼ぶのだろうか。筋みちにオリジナリティのダイナミックさが欠けているので、剽窃にしか見えないので、とまどったあげくに失笑してしまう。
唯一のみどころは、Bellの歌謡ショーの部分だ。実際に歌っている中村佳穂には十分に惹きつけられた。
それにしてもこの大作には、あざとさを感じてしまった。
監督 細田守
公開 2021年7月
私的オススメの映画
(著作権)オリジナル画像の著作権の侵害を意図するものではありません。